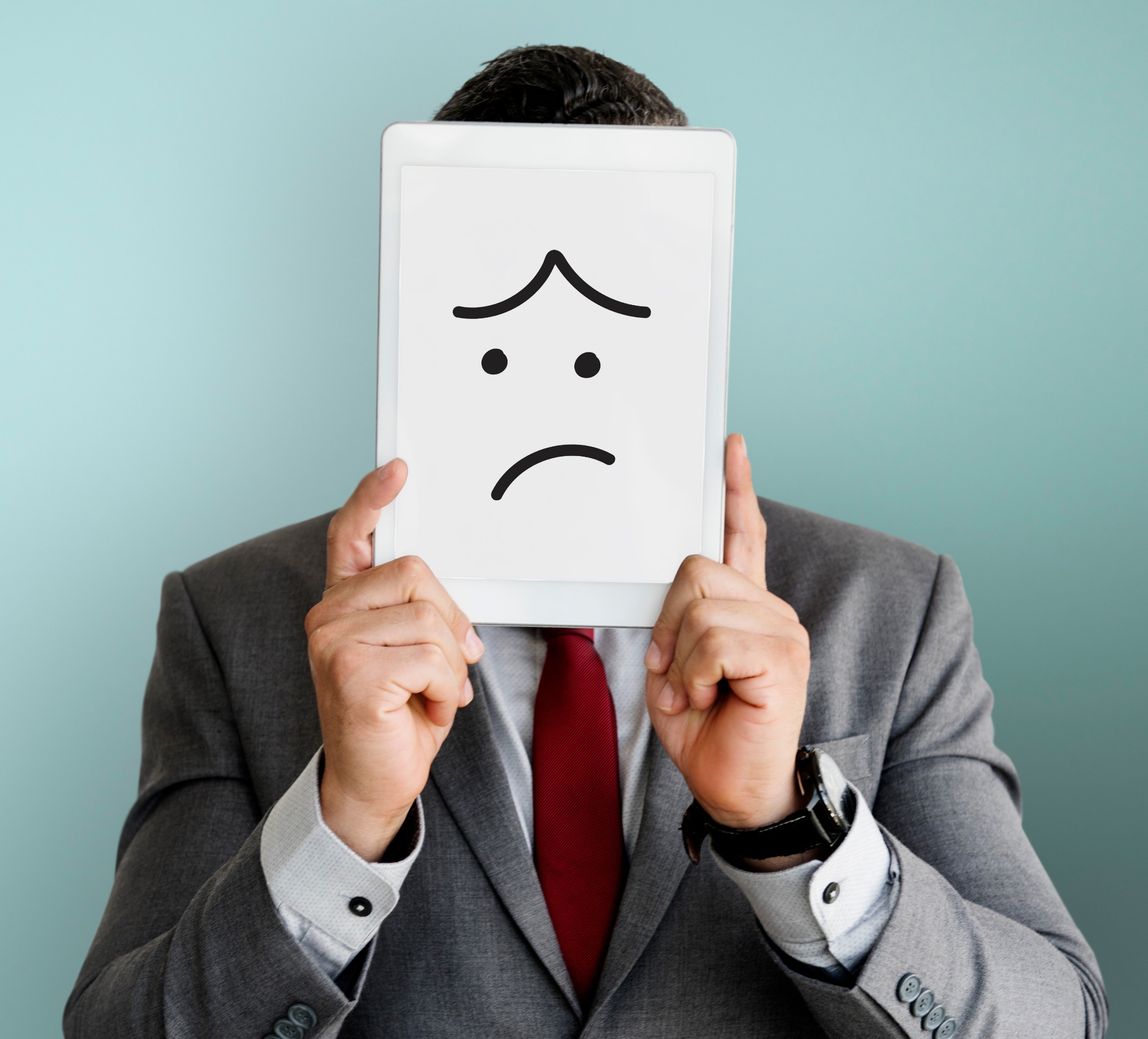
当社では、長くハラスメントに関する研修を提供してきています。ゲーム性のあるツールという点でも、「ボスの品格(パワハラ)」から始まり「ボスは貧弱(逆パワハラ)」、そして今年は「ふぞろいな客人たち(カスハラ)」を発売しました。
私たちが兼ねてからお伝えしていることですが、ハラスメントには元々細かな種類分けがあるわけではありません。パワハラも逆パワハラもカスハラも和製英語で認知活動のために便宜的に名前が付けられたもので、労働基準局のワーキンググループの「流行らせる」という議事録もしっかり残っています。
ですので、本来的にはハラスメントにはこうした分類はなく、単に「ハラスメント(嫌がらせ)」なわけですから、「ハラスメントを防止したい」「職場の環境を良くしたい」といったときに「他社とどう違うのか」「どのツールが良いのか」とお悩みになる方が増えるのは当然です。
また、ハラスメント研修はどこでも実施している研修ですが、実はその考え方にはさまざまなものがあります。法令理解に重きを置くところもあれば、法令順守に重きを置くところもあります。また、「あなた方は潜在的な加害者です」とする研修もあれば、「あなた方はハラスメントを見つけたらそれを止める立場です」とする研修もあります。
なので、今回は、そうした事情もあり、ハラスメント研修を比較してみたいと思います。まず、前半はアプローチの違いについて、後半は、当社内のコンテンツの比較についてです。
アプローチの違いについて
あなたは潜在的な加害者であるというアプローチの危険
当社のハラスメント研修では、「あなたは潜在的な加害者である」というメッセージが却ってハラスメントを増やすことがあるという研究知見から、「あなたは潜在的な加害者である」という風には研修参加者を扱いません。それが「心理的安全性の高い研修」なのです。
では、どうするかというと、ハラスメントの加害者と被害者を見ている第三者(バイスタンダー)であれば、どう介入するかを考えます。これを「第三者介入」と呼びます。
これによって、「あなたは潜在的な加害者である」というメッセージが消え、研修参加者は「職場の問題をともに解決する仲間である」というメッセージに変わります。
詳しくは、以前の代表コラムに記載していますので、ご参照ください。
ハラスメント研修に対する直感に反する研究結果(2)-バイスタンダーになる研修が効果的-
もちろん、これまで「潜在的な加害者」と呼び続けているから継続したいという会社様を止めることはしませんので、教育の継続性の観点と心理的安全性を担保しハラスメントを減らす観点の双方からご判断されるとよいと思います。
第三者介入ならではの利点
最後に、「第三者介入」ならではの利点をお伝えしましょう。通常のハラスメント研修の目的は「意識変容」です。意識は間接的に行動になるとは言え、直接的に「行動」を扱うハラスメント研修は多くありません。ある意味、決められていることだからやっておけばよいと諦められているところもあります。(現に、ハラスメント研修には予算も時間も割り振られにくいです。)
ただ、私たちはそれで良いとは思っていません。だから私たちは「どう介入すれば良いか」という「行動」につながる研修を実施しているのです。これが他社様との最大の違いかもしれません。
当社のハラスメントに関するコンテンツの比較
ボスの品格とボスは貧弱の比較
まず、「ボスの品格」と「ボスは貧弱」の比較です。これらについては「誰向けか」という点でお悩みが多いようです。
前提として、パワハラと逆パワハラは、名前が違いますが、いずれもパワハラに属し、パワハラはハラスメントに属します。パワハラは厚労省の定義では、上司から部下という指向が設定されていますが、本来的には部下から上司という指向も同僚間という指向も含みます。
当社の「ボスの品格」は上司の立場の人が部下に対してハラスメントかどうか怪しい(グレー)行動をしています。それを見てどうかを判断するのが研修の参加者の立場です。なので、部下目線の参加であっても、上司目線の参加であってもそして混合であってもまったく問題はありません。
ただし、パワハラの主体が上司なのか、部下なのかという点はもちろん異なりますので、どちらのゲームが良いかという視点ではなく、どういうパワハラについて考えさせたいかといった目的に応じて検討いただけるとよいと思います。
ボスの品格とふぞろいな客人たちの比較
次に、「ふぞろいな客人たち」との比較です。まず、カスハラは顧客から社員へのハラスメントですが、東京都の条例では、社員が外で顧客として他社にカスハラをしないといった点も含み、これが努力義務になっています。ただ、やることは人が人として場所を問わず他人が嫌がることをしないというのがゴールですからその他のパワハラと大きく違うかというとあまり違いません。
ただ、私たちも日本の法令や官公庁の発信は意識する必要がありますので、カスハラに固有の「長時間の拘束」や「リピート性」を考慮する必要があります。(逆にどうしてパワハラ側にそれがないのかは不思議です。)
「ふぞろいな客人たち」では、「長時間の拘束」や「リピート性」を実現するために「時間」の概念を設けました。また、一方でゲーム的な要素を排除し、いわゆる「物語の面白さ」で興味喚起する仕立てにしました。これにより、短時間化を実現しています。(コンプライアンス系の研修は実に短時間が要求されるのです。)
関連リンク
第三者介入の観点で良い職場を実現する-ハラスメント防止研修-
公開日: 2025年8月5日





